川口和久氏が、プロ1年目から制球を改善した経験をもとに、コントロール向上のための具体的なフォーム修正と投球理論を解説します。下半身の使い方・肩と腰のライン制御・ラインの可視化など、サウスポー特有の視点で語られる内容は、実戦的かつ指導にも応用できるものです。
- 1. プレートの立ち位置と肩のラインの重要性【00:10】
- 肩の高さを保つことが制球の基礎
- 体重を軸足に残す感覚
- 2. 腰の回転とヒップ先導の意識【03:55】
- ヒップの先に向かって投げる
- 膝の位置で腰の動きを制御
- 3. 回転の使い分けでコースを投げ分ける【06:30】
- インコース=回転量大、アウトコース=抑えめ
- クロスファイアよりもライン制御が重要
- 4. 力を溜める・切る|腰主導の投球フォーム【07:45】
- 膝と股関節で腰を「切る」動作
- 体重移動よりも「止める」意識
- 5. 狭いステップ幅で制球力を得た経験【09:04】
- ステップ幅7歩→5歩への変更
- 体重移動を抑えた制球型フォーム
- 6. 見えないラインへの投球意識【10:11】
- 目標を“曲がる前”に設定
- ラインに乗せる感覚が制球を安定させる
- 7. 高めの力強いストレートと投球テンポ【13:19】
- 真ん中高めは使い方次第で武器になる
- 7秒以内のテンポがテンポの基準
プレートの立ち位置と肩のラインの重要性【00:10】
肩の高さを保つことが制球の基礎
ステップ時に肩のラインが下がると、手が遅れてボールが浮きやすくなると指摘されています。力を無駄にしないためにも、ステップ後に肩を平行に保つことが重要と語られています。
体重を軸足に残す感覚
打者と同じく、投手も体重を軸足に一度乗せる意識が必要であり、それにより強いボールが投げられると述べられています。
腰の回転とヒップ先導の意識【03:55】
ヒップの先に向かって投げる
川口氏が提唱するのは「投げたい方向はヒップの先」。膝を使って腰を送り出すことで、自然なフォームで球が投げられるようになるといいます。
膝の位置で腰の動きを制御
膝の向きで腰の開きを調整することで、インコースとアウトコースの投げ分けも可能に。疲労時は回転が不十分となり、ボールがアウトコースに流れる例も紹介されています。
回転の使い分けでコースを投げ分ける【06:30】
インコース=回転量大、アウトコース=抑えめ
インコースへは腰をフル回転させ、アウトコースへは回転量を抑える。この使い分けがコントロールの基盤になると解説されました。
クロスファイアよりもライン制御が重要
左投手の代名詞ともいえる「クロスファイア」よりも、外角のコントロールを重視して練習していたとのことです。
力を溜める・切る|腰主導の投球フォーム【07:45】
膝と股関節で腰を「切る」動作
膝の向きを制御し、腰の回転を一気に引き出す方法が紹介されました。これにより、上半身へのエネルギー伝達がスムーズになり、球に力が加わると述べられています。
体重移動よりも「止める」意識
股関節が硬い選手が多いため、「体重を移動させる」よりも「止めてから切る」方が実戦的であると語られました。
狭いステップ幅で制球力を得た経験【09:04】
ステップ幅7歩→5歩への変更
プロ1年目でコントロールを改善するため、ステップ幅を通常より大きく減らしたエピソードが紹介されています。
体重移動を抑えた制球型フォーム
ステップを狭めたことで、余計な動きが減り、再現性の高いフォームとなったと話されています。
見えないラインへの投球意識【10:11】
目標を“曲がる前”に設定
変化球は最終的な着地点よりも、曲がる前のラインを意識して投げるべきと語られています。見えないラインをイメージすることで制球力が向上すると述べています。
ラインに乗せる感覚が制球を安定させる
まっすぐも変化球も、意識するラインにボールを乗せるイメージが重要とされ、感覚的なライン把握力がカギとされています。
高めの力強いストレートと投球テンポ【13:19】
真ん中高めは使い方次第で武器になる
高めのストレートは「力があるボール」であれば有効であり、打者にとっても対応が難しいと語られています。
7秒以内のテンポがテンポの基準
投球テンポも重視しており、「キャッチャーが返球してから7秒以内」が理想のテンポとされていました。速いテンポは守備のリズムにもつながります。
この動画から学べること
- 肩の高さを保ち、軸足に体重を残すフォーム構築
- 「ヒップの先」に向けて投げる回転主導のコントロール術
- 腰の切り返しで球威と制球を両立させる方法
- 見えないラインを意識することで安定した制球を実現
- 高めストレートの活用とテンポ重視の投球スタイル
これらの技術・意識が気になる方は、ぜひ動画でフォームや動きを実際に確認してみてください。左投手ならではのアプローチが多数詰まった内容です。
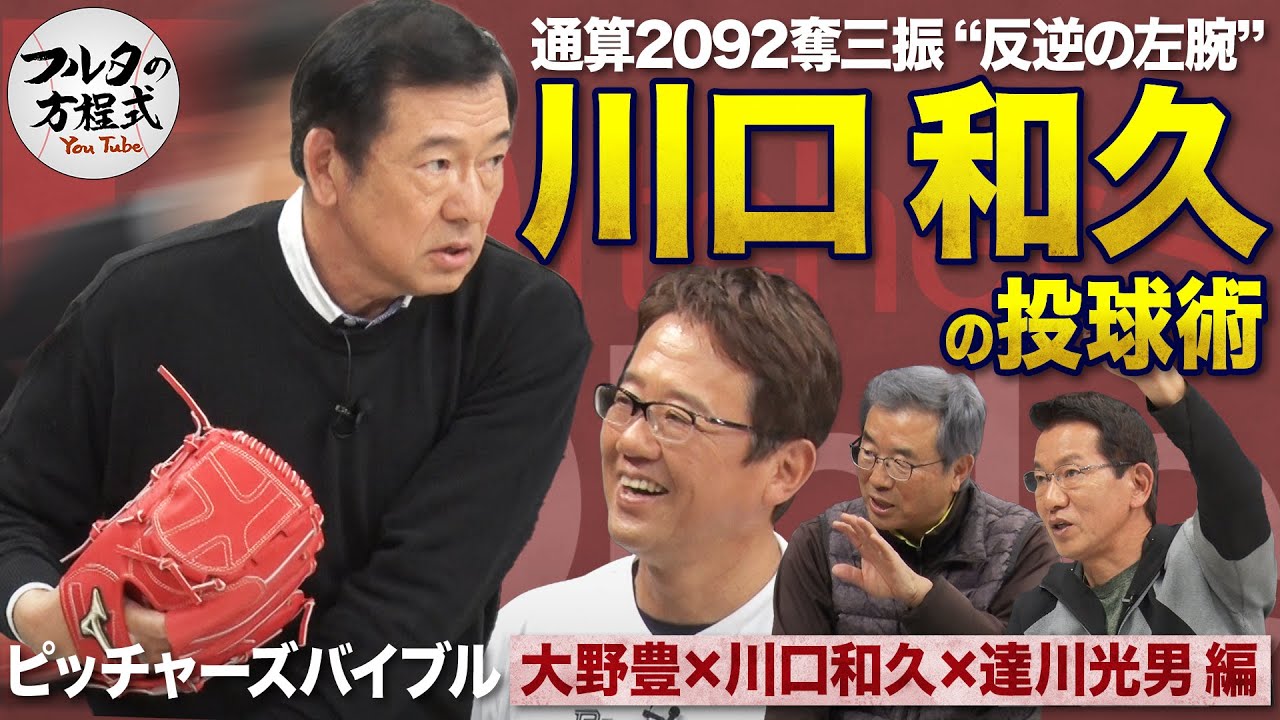

コメント