和田毅が行っているトレーニングや投球フォームの意識、下半身主導の動作の重要性について語られています。スライダーやチェンジアップなど多様な球種について、それぞれの握り方と感覚の違いを具体的に解説しています。
- 1. ウエイトと走り込みのトレーニング 00:01
- 基本的な種目と強度のバランス
- 走り込みと体力づくりの考え方
- 2. 投球のコントロールと体の使い方 02:48
- インコースへの投げ方の感覚
- 重心と動作解析からの学び
- 3. 出力の中心と怪我予防の意識 06:00
- 体幹主導の動作と力の伝達
- マウンド環境の違いと肘への影響
- 4. 球種ごとの握りと投げ方の違い 08:38
- スライダー・チェンジアップ・フォーク
- 握り方の工夫と投球フォームとの関係
- 5. カーブの握りと他選手との違い 12:16
- カーブの親指と指先の位置
- 自分に合った握りの探求
- 6. ワインドアップとコントロール向上の意識 13:32
- 高校時代からのフォームの変化
- コントロールと球速のバランス
- 7. キャッチボールと感覚の調整法 15:57
- フォーム修正と連続精度のチェック
- 距離別の意識と体の使い方
ウエイトと走り込みのトレーニング 00:01
基本的な種目と強度のバランス
和田選手はベンチプレス、スクワット、デッドリフトなど、一般的なウエイト種目を取り入れており、年齢と体の状態に応じてベルトを使うなど調整しながら行っていると述べています。
走り込みと体力づくりの考え方
大学時代からポール間走を中心としたインターバルトレーニングを継続しており、自身には合っていたと語っています。長距離走については、目的に応じてエアロバイクなどを活用した有酸素運動が有効と考えているとのことです。
投球のコントロールと体の使い方 02:48
インコースへの投げ方の感覚
ターゲットに対するイメージを持ちながら、振り切った結果としてそこに到達する感覚を大事にしていると語っています。繰り返しの中で身体に感覚を染み込ませているとのことです。
重心と動作解析からの学び
下半身の動きが正しく使えているかを重視し、下から上への力の連動がスムーズなときに最も効率よく出力できると述べています。データでの波形の違いを参考に、動作のブレを確認することも行っているようです。
出力の中心と怪我予防の意識 06:00
体幹主導の動作と力の伝達
現在は体幹を中心に据え、そこを起点にして上下を連動させるイメージを持って投球していると説明しています。小さな動きで投げることで怪我を防ぎ、効率的なフォームを実現することを目指しているとのことです。
マウンド環境の違いと肘への影響
メジャーの硬いマウンドは下半身の可動が制限されやすく、それが肘や肩への負担につながると指摘しています。日本でもマウンドが硬化してきたことで、この影響が少しずつ和らいできたとも語っています。
球種ごとの握りと投げ方の違い 08:38
スライダー・チェンジアップ・フォーク
スライダーは中指主体、チェンジアップは若干シュート気味の動きで、浅めの握りを意識。フォークはチェンジアップ寄りのイメージで、浅く添えるような握りになっていると説明しています。
握り方の工夫と投球フォームとの関係
各球種ごとに投げ方との一貫性を重視しており、握りによってフォームが変わることを避けるよう工夫しています。特定の握りに固執せず、自身のフォームに最も合う形を模索してきたとのことです。
カーブの握りと他選手との違い 12:16
カーブの親指と指先の位置
親指の位置や持ち方には個人差があり、工藤公康氏や斎藤和巳氏など、先輩選手との違いにも触れながら、自分に合った形を試行錯誤したと述べています。
自分に合った握りの探求
スライダーやチェンジアップでも様々な持ち方を試した結果、すべての球種でフォームが統一される握りを重視してきたと話しています。投球の見た目がバレないことも大事な要素としています。
ワインドアップとコントロール向上の意識 13:32
高校時代からのフォームの変化
高校時代はセットポジション中心でしたが、プロ入り後はワインドアップの方が勢いが出ると感じて以降、最終的まで継続していると述べています。
コントロールと球速のバランス
コントロール向上のために投げるというより、良いフォームを追求した結果として制球が安定するという考え方を持っているとのことです。
キャッチボールと感覚の調整法 15:57
フォーム修正と連続精度のチェック
自分のイメージ通りに球が続けて投げられるかをキャッチボールで確認しており、調子の良い時は70球以上連続して安定することもあると語っています。
距離別の意識と体の使い方
50m程度の距離でのキャッチボールを重視し、下半身を使って体全体で投げる意識を持つことが大切だとしています。傾斜やマウンドによる変化への対応も含めて、柔軟な調整を意識しているようです。
この動画から学べること
- ウエイトトレーニングと走り込みの具体的なメニューと考え方
- 下半身主導の動作解析とフォーム調整のポイント
- スライダー・チェンジアップ・フォークなど各球種の握り方と意識
- ワインドアップへの移行とフォームの安定性の向上
- キャッチボールによる感覚調整と投球精度の確認方法
これらが気になる人は、ぜひ実際の映像でニュアンスを確認してみてください。また、関連動画では別のプロ選手が同じテーマについて異なるアプローチを語っているので、自分に合った考え方を見つけてみましょう。
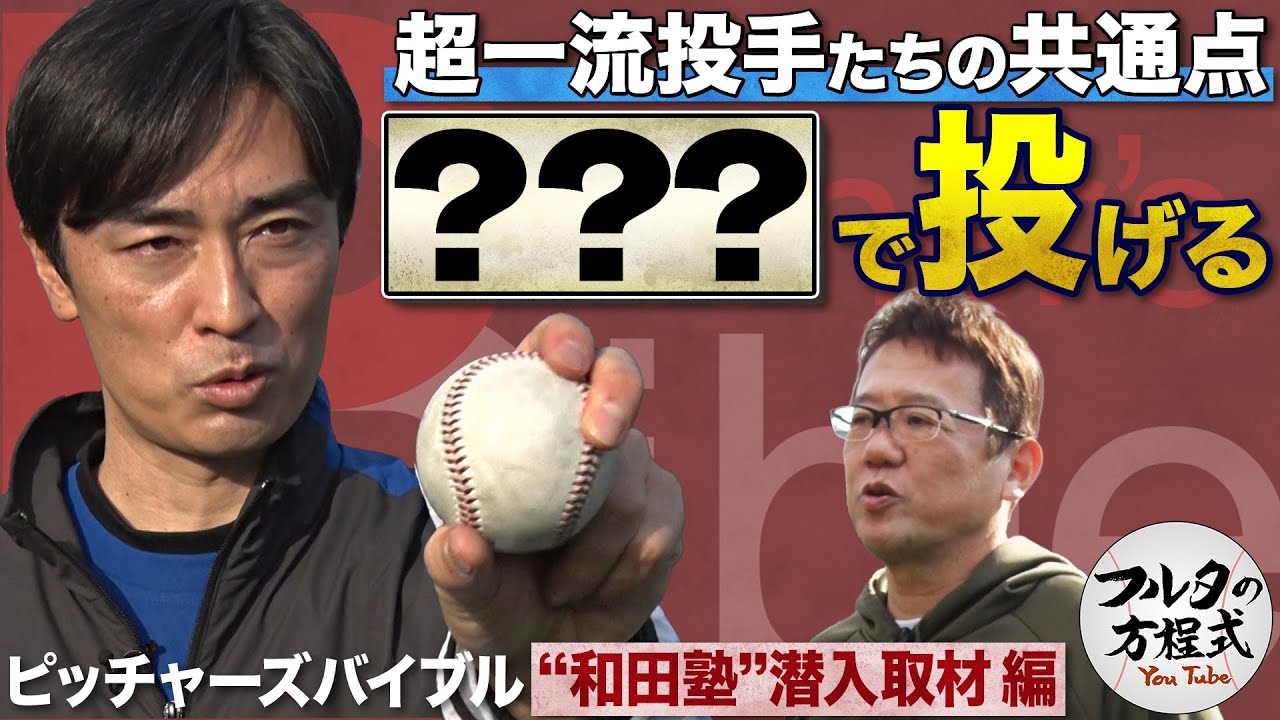


コメント