平成の怪物・松坂大輔が、自身のピッチングメカニックや意識の変遷、身体との向き合い方を語った対談形式のインタビューです。ピッチングフォームにおけるリズムとバランス、軸足の使い方、力の抜き方、さらにはフォーム改良への考え方など、投手育成に役立つ要素が詰まった内容となっています。
- 1. フォームの中で大切にしていたこと 00:00
- リズムとバランスを一貫して意識
- テンポは変えてもフォームは崩さない
- 2. 軸足の使い方と“蹴らない”意識 02:29
- 交通事故の影響と膝の弱さ
- “蹴らずに残す”がフォームの原点
- 3. 投球における脱力と力感のコントロール 07:53
- 腕の振りを早くするための“抜き”の技術
- ゆっくり大きく動かす練習
- 4. コントロールを身につけた練習法 17:42
- ホームベースへの“当てる練習”
- 緩いカーブでリズムを整える
- 5. 自分の身体との向き合い方 18:56
- 自分の弱点を理解し最適解を探す
- “やらされる練習”から“考える練習”へ
フォームの中で大切にしていたこと 00:00
リズムとバランスを一貫して意識
松坂選手はフォームの中で「リズム」と「バランス」を常に重視しており、フォーム自体のテンポやスピードは一切変えず、安定した動作を意識していたと語ります。
テンポは変えてもフォームは崩さない
相手打者に対しては、フォーム以外のテンポや間で変化を与えることで、打ち取る工夫をしていたとのことです。
軸足の使い方と“蹴らない”意識 02:29
交通事故の影響と膝の弱さ
幼少期の交通事故により右膝に力が入りづらく、右足で「蹴る」動作ができなかったことから、フォームの工夫が始まりました。
“蹴らずに残す”がフォームの原点
「右足を離すな」と指導されたことがきっかけで、プレートに足を残したまま投げる意識が浸透。これが横浜高校のピッチャースタイルにも影響を与えたと明かしています。
投球における脱力と力感のコントロール 07:53
腕の振りを早くするための“抜き”の技術
投げる直前に力を抜く意識を強く持ち、「抜けた腕」から自然に加速して振ることを心がけていたとのことです。
ゆっくり大きく動かす練習
キャッチボールではスローボールで「ゆっくり大きく」「途中でふっと抜く」動作を取り入れ、力のコントロールを体得していたと語ります。
コントロールを身につけた練習法 17:42
ホームベースへの“当てる練習”
高校時代、ホームベース上にボールを置いてそれを当てる練習を繰り返すことで、「どこで離せば当たるのか」の感覚を養ったと話します。
緩いカーブでリズムを整える
プロ入り後も「緩いカーブで投げるリズム」を大事にしており、そのタイミングが一番自然に力を伝えられると語っています。
自分の身体との向き合い方 18:56
自分の弱点を理解し最適解を探す
「膝が使えない」という弱点を自覚した上で、軸足や押し込みの仕方などを工夫し、より自然に力が伝わるフォームを確立していきました。
“やらされる練習”から“考える練習”へ
成長の転機は、「練習の意味を考えるようになったこと」。指導の意図を理解し、自分なりに答えを導く姿勢が、プロとしての確かな土台を築きました。
この動画から学べること
- フォーム内のリズムとバランスを重視する姿勢
- 身体的特徴(膝の弱さ)を逆手に取ったフォームの工夫
- 投球時の「脱力」と「抜き」の重要性
- 力の出し方を理解するスローボールの活用法
- コントロールを養う具体的な的当て練習
- 練習の意味を考え、自ら答えを見出す姿勢
技術面と精神面の両面にわたる内容は、投手を目指す選手だけでなく、指導者にとっても大いに参考になります。ぜひ動画で動きのニュアンスや表情も合わせてご覧ください。
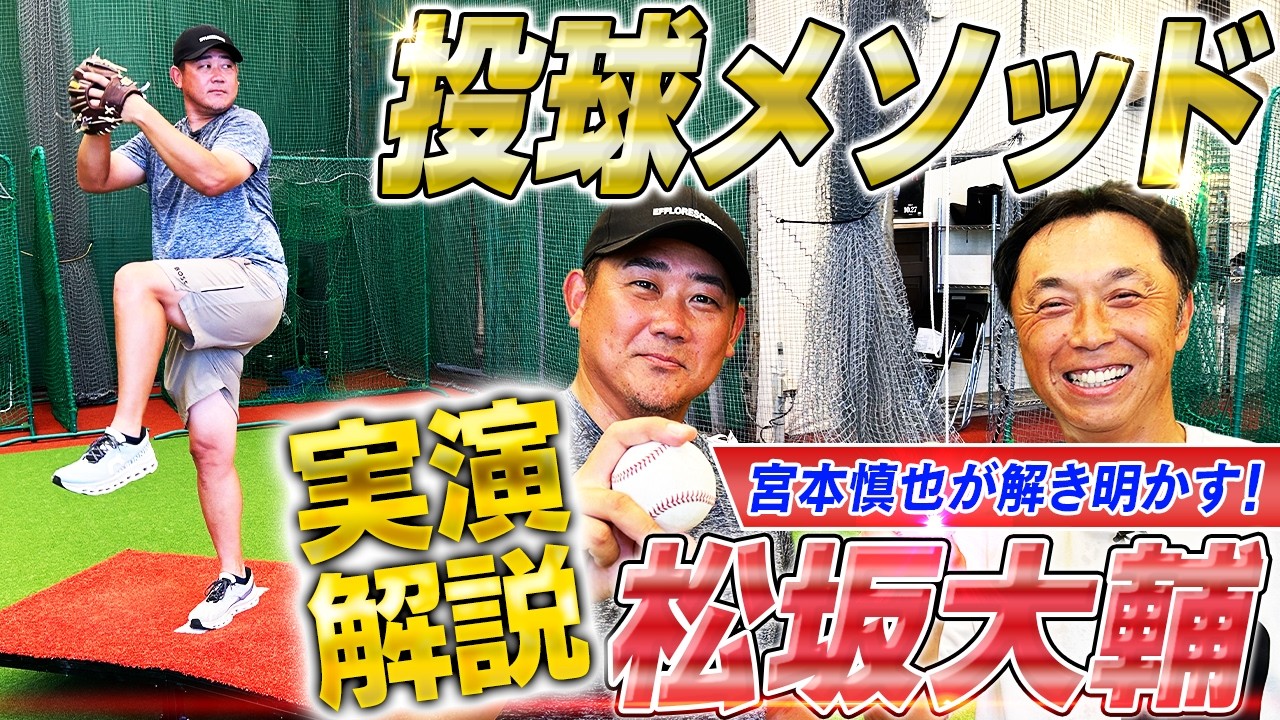


コメント