✔ 「球速とコントロールを両立するには?」
✔ 「ストレートとカーブだけで勝つ投手の共通点とは?」
✔ 「練習を見せないことが、投手の武器になる?」
伝説の投手たちが語る、 投球の極意 。その核心に迫る!
- カーブを覚えたきっかけと球種の哲学
- コントロールを極めるために必要なこと
- 「練習は見せない」投手としての戦略
- 速球投手が持つ、共通の特徴とは?
- 投手にとって、環境の変化は何をもたらしたのか?
【動画のポイントまとめ】
1. カーブを覚えたきっかけと球種の哲学
✔ カーブは仕方なく覚えた?
- 高校時代に見た「衝撃的なカーブ」 に影響を受けた
- スライダーっぽい速いカーブ を見て、「投げたい!」と感じた
- カーブが武器になれば、ストレートの威力がより生きる
✔ 「投手は、投げられないものを投げてみたくなる」
- 投手の成長は「できないことへの挑戦」から始まる
- 周囲に優れた投手がいると、自然と新たな球種を覚える
✔ カーブの結論
- 「ストレートの質を活かすため」にカーブを覚えた投手が多い
2. コントロールを極めるために必要なこと
✔ 「コントロールは自信から生まれる」
- 思ったところに投げられるという 確信が最も重要
- 迷いがあると ボールがブレる
✔ 「ブルペンでのコントロールは100%ではない」
- 試合では、環境が変わることで制御が難しくなる
- ブルペンで80%の精度なら、試合では使えない
- 観客・バッター・プレッシャーの中で、自信を持てる練習が必要
✔ 「ランナーが溜まっても、投げられるかが勝負」
- ブルペンでは完璧でも、試合では違う
- 精神的に揺さぶられないメンタルが重要
✔ コントロールの結論
- 技術だけではなく、「試合で通用する自信」が不可欠
3. 「練習は見せない」投手としての戦略
✔ 「練習しているのに、していないように見せる」
- 「あいつは練習してないのに、なんであんな球を投げられるんだ?」
- そう思わせることが、投手としてのプライドだった
✔ 「性格を見せないことも、投手の武器」
- マウンド上では「何を考えているかわからない存在」でいることが大切
- 投手が読まれないことは、バッターへのプレッシャーになる
✔ 「相手にとって予測できない投手になる」
- どんな球を投げてくるかわからない
- どのタイミングで仕掛けてくるかわからない
- 「読まれない投手」が、最も厄介な存在
✔ 練習哲学の結論
- 投手は「練習量」ではなく「練習を見せないこと」も戦略になる
4. 速球投手が持つ、共通の特徴とは?
✔ 「球速とコントロールを両立するのは難しい」
- 速い球を投げる投手は、制球に苦労することが多い
- その中で 「ストレートとカーブだけ」で勝てる投手 もいる
✔ 「球種が2つだけの投手が、なぜ勝てるのか?」
- ストレートとカーブだけで勝負できるのは、「球の質」が違うから
- 変化球に頼らなくても、ストレートの威力とコントロールで勝負できる
✔ 「フォークを投げられなかった理由」
- 指の長さが影響する
- フォークは挟める指が長いほど有利
- 手が小さい投手は、フォークではなく別の球種で勝負する
✔ 速球投手の結論
- ストレートの威力と精度があれば、球種は少なくても勝負できる
5. 投手にとって、環境の変化は何をもたらしたのか?
✔ 「かつての野球環境」
- 土の上で野球をしていた時代
- 人工芝や屋根付きの球場が当たり前になった
✔ 「環境の変化による影響」
- 雨の影響を受けない球場になったことで、投手のスタイルも変わった
- かつては雨上がりの試合での制球が難しかった
✔ 「環境の変化とピッチングの関係」
- 昔の投手は「悪条件でも投げる技術」が求められた
- 現代では、均一な環境で「精密な投球」が求められる
✔ 環境の結論
- 時代とともに、投手の求められる技術も変化している
【結論:投球の本質は「読まれないこと」と「自信」】
✔ 投手は「読まれない存在」でいることが武器になる
✔ ストレートとカーブだけで勝負する投手には共通点がある
✔ コントロールの良さは「試合で投げられる自信」から生まれる
✔ 練習を見せないことで、相手に「謎の存在」としてプレッシャーを与える
✔ 時代の変化とともに、投手のスタイルも変わってきた
動画はこちら → [動画リンク]
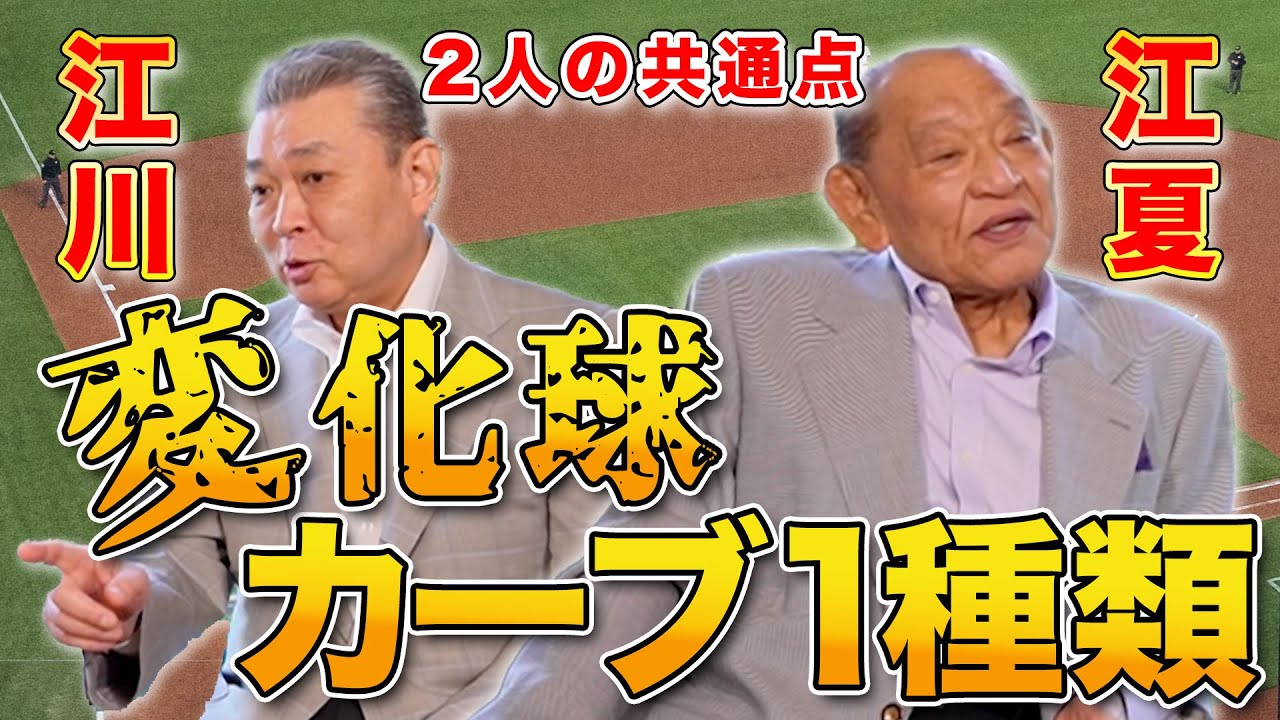


コメント