コントロールを改善するための練習方法や身体の使い方について、工藤公康氏を中心として自身の経験とともに具体的に語っています。フォームの再現性と身体の連動を高める投球練習の重要性について、実例を交えながら解説されています。
- 1. コントロールを磨くための段階的キャッチボール【00:00】
- 10球連続成功の反復練習
- 感覚を磨くための短距離投球の工夫
- 2. 投球フォームの再現性とバランス【01:31】
- フォーム・タイミング・バランスの関係性
- 段階的に整理する練習の意義
- 3. リリースと着地の時間差を活かす動作設計【03:45】
- 着地後の時間差でバッターを欺く
- ハムストリングや内転筋の意識的使用
- 4. ダンボール理論とストライクゾーンの空間認識【12:43】
- 投球動作を線でとらえる考え方
- ストライクゾーン内で動作を収める意識
- 5. コントロール向上と投球確率の考え方【15:19】
- 再現性を高める反復練習の重要性
- 高確率で投げる感覚の習得
コントロールを磨くための段階的キャッチボール【00:00】
10球連続成功の反復練習
中学生や高校生に対しては、10メートル程度の距離からキャッチボールを始め、構えた位置に正確に10球連続で投げられるまで繰り返す練習が推奨されています。連続成功したら一歩下がり、また繰り返すという段階的な方法で、感覚と精度の向上を目指します。
感覚を磨くための短距離投球の工夫
「力加減が100か0しかない」現代の若い選手に対し、短距離での調整練習が重要とされます。段階的な練習を通して、投球フォームや力加減の感覚を養うことができます。
投球フォームの再現性とバランス【01:31】
フォーム・タイミング・バランスの関係性
コントロールが悪かった時期は、リリースタイミングが一定でなく、フォームや力の出し方にもばらつきがありました。改善には、バランスと再現性を意識した練習が必要であり、その過程で効率的な動作の発見が大きな意味を持ちます。
段階的に整理する練習の意義
フォーム、タイミング、リリースといった要素を分けて考えることで、それぞれの要素を安定させ、最終的にマウンド上で統合された再現性の高いフォームを作り上げることが可能になります。
リリースと着地の時間差を活かす動作設計【03:45】
着地後の時間差でバッターを欺く
ピッチャーが踏み出してからボールをリリースするまでの「時間差」を意識することで、打者にとってタイミングが取りにくくなります。これはコントロール向上にも寄与する要素とされています。
ハムストリングや内転筋の意識的使用
着地後に左足が内側に引かれることで、ハムストリングが収縮し、膝が伸びにくくなります。これにより安定したリリースポイントを確保する動作を作り出すことが可能です。内転筋の収縮も回転動作に関与しており、上級者は無意識あるいは意識的にこれを活用しています。
ダンボール理論とストライクゾーンの空間認識【12:43】
投球動作を線でとらえる考え方
ボールのリリースを「点」ではなく「線」で捉える意識が、コントロールの安定化に繋がるとされています。腕の軌道や体の使い方が線的に連続していることが重要です。
ストライクゾーン内で動作を収める意識
体全体が「ダンボール」の中に収まって移動するイメージで、バックスイングからリリースまでをストライクゾーン内に納める意識を持つことで、ブレのない投球動作が可能になります。
コントロール向上と投球確率の考え方【15:19】
再現性を高める反復練習の重要性
球数制限が叫ばれる中でも、「投げなければコントロールは良くならない」と語られています。フォームや体の使い方の再現性を高める練習を重ねることが最も重要とされています。
高確率で投げる感覚の習得
ストライクを取る確率を高めることが防御率の向上に直結するとされ、キャッチボールでも一定のゾーンにボールを集める意識を持つことが必要です。距離が伸びても身体の同じ側にボールを集める習慣が有効とされます。
この動画から学べること:
- 段階的キャッチボールによるコントロール強化法
- フォームとタイミングの再現性を高める意識と練習法
- 着地とリリースの時間差を活かす投球動作の工夫
- 内転筋・ハムストリングの使い方と投球への影響
- ストライクゾーン内で動作を収める「ダンボール理論」
これらの内容をさらに詳しく知りたい方は、実際の映像で工藤氏の言葉や動きを確認してみてください。また、関連動画では同様のテーマを別の視点で解説している内容もありますので、自身に合ったアプローチを見つける際の参考になるでしょう。
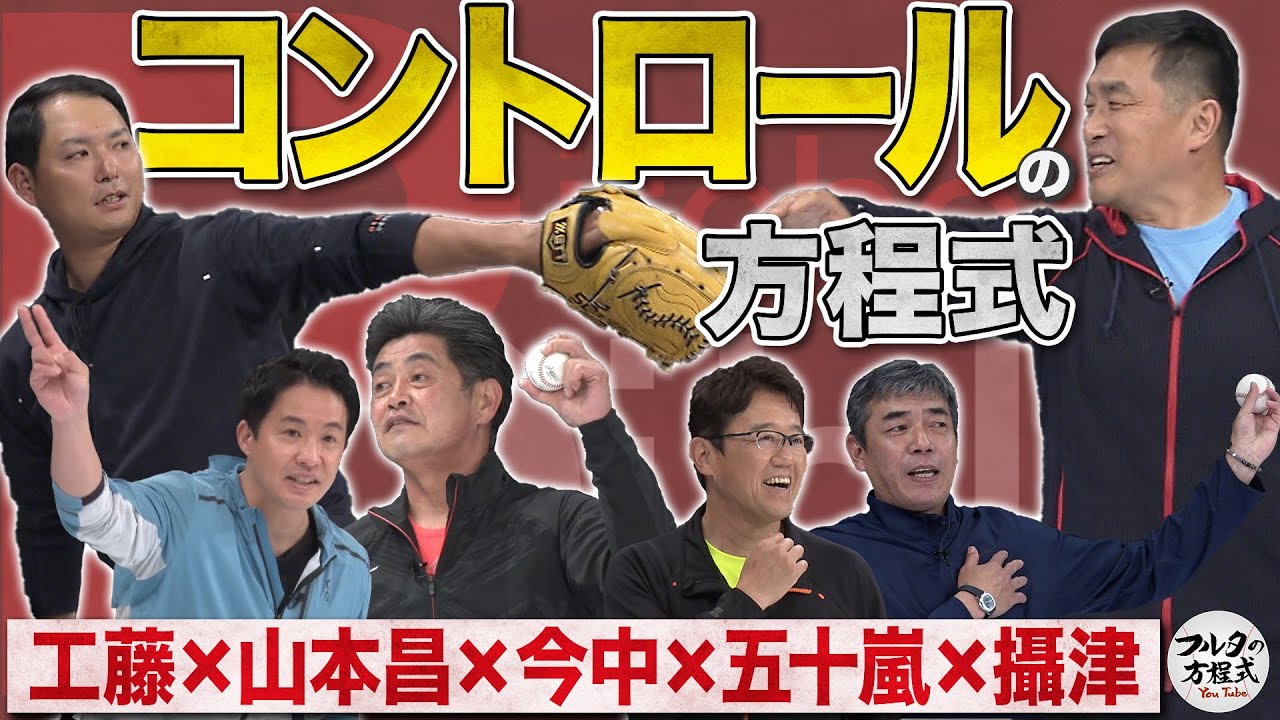


コメント