歴代ゴールデングラブ受賞者・宮本慎也、石井琢朗、小坂誠、鳥谷敬、源田壮亮が、守備動作における足の使い方と、バランスを崩さずに送球するための考え方やステップの工夫などの実戦的な守備技術を解説しています。
- 1. 足の使い方と体の連動性【00:01】
- 体より足を先行させる意識
- 投げ終わりまでの動きとバランス
- 小刻みなステップでリズムを作る
- 2. 力の抜き方と姿勢のバランス【03:16】
- 上半身の力を抜いて足を使う
- 投げるための体勢の整え方
- 正面の打球処理と間の取り方
- 3. 握り替えの工夫とステップの時間配分【09:25】
- 握り替えを早めるための練習法
- ステップで時間を稼ぐ意識
- 死んで取ることでのコントロール向上
- 4. 捕球位置の意識と視野の確保【12:38】
- 捕球位置と左足の関係
- 投げる方向に応じた捕球位置の変化
- 視界とスムーズな動作の両立
- 5. シングルハンド捕球と技術理解の重要性【15:57】
- 現役選手に多いシングルハンド処理
- 止まる技術と身体の使い方
足の使い方と体の連動性【00:01】
体より足を先行させる意識
守備では、状態が前に突っ込まないように意識しながら、足を先に出す動きを練習で徹底していると述べています。足が先行し、体が遅れてついてくることで、下半身主導の動作になるという感覚です。
投げ終わりまでの動きとバランス
投げ終わりに向かって自然に数歩進むイメージを持つことで、上半身に頼らず、足を活かした投球ができると語られています。逆に、投げた直後に後ろに戻るような動きは、上半身主導になっている証拠と捉えられています。
小刻みなステップでリズムを作る
ボールに対して衝突しないために、最後に小刻みなステップを入れて間を作る工夫も紹介されています。これによりリズムよく捕球・送球へ移行しやすくなるといいます。
力の抜き方と姿勢のバランス【03:16】
上半身の力を抜いて足を使う
走る・投げる動作の中で上半身に力が入りすぎるとバランスを崩しやすくなるため、なるべく力を抜き、足で動きをコントロールする意識が大切だと話しています。
投げるための体勢の整え方
「投げる」ではなく「足で運ぶ」という感覚を持つことで、スムーズに送球動作に移行できるようになります。これは全員に共通する意識だとまとめられています。
正面の打球処理と間の取り方
横の打球と異なり、正面の打球では間を取りづらくなるため、力を抜いて下からグローブを出すように意識することで対応しています。
握り替えの工夫とステップの時間配分【09:25】
握り替えを早めるための練習法
捕球後すぐに握り替えを行うためには、「死んで取る」ようにグローブに当てると、自然に手元に球が残り、無理なく握り替えが可能になると語られています。
ステップで時間を稼ぐ意識
足のステップの中で時間を作ることで、上半身の動作にも余裕が生まれ、正確な握り替えが可能になります。急ぎすぎず、下で間を作るのがポイントです。
死んで取ることでのコントロール向上
強く弾いたり、意図しない方向へ飛んでしまうのは、力が入りすぎていることが原因とされ、グローブに優しく当てて“死んで取る”ことで安定した処理が可能になります。
捕球位置の意識と視野の確保【12:38】
捕球位置と左足の関係
左足が前に出すぎるとバランスを崩すため、捕球時の位置取りとしては、つま先が少し出る程度が理想とされます。捕球後の右足の出やすさを重視した位置取りです。
投げる方向に応じた捕球位置の変化
基本はやや左寄りでの捕球が多いですが、打球の方向や送球方向によって調整し、自分の動きやすい位置で捕ることを優先しています。
視界とスムーズな動作の両立
ボールを視野に入れながら、身体のバランスを保てる範囲で捕球位置を選び、突っ込んでも目線で追える範囲を意識することが重要とされています。
シングルハンド捕球と技術理解の重要性【15:57】
現役選手に多いシングルハンド処理
現在のプロ野球選手の中でも、シングルハンドでの捕球が多くなってきており、技術的な準備や理解がないと参考にしづらいため、技術を理解してから取り入れるべきという意見も出されていました。
止まる技術と身体の使い方
シングルで捕球する際に、しっかり止まって処理できる技術や身体の使い方が必要であり、力まずにグラブでボールを受ける柔軟性が求められます。
この動画から学べること
- 下半身主導の守備動作と足を使ったステップの考え方
- 力を抜いてバランスを保つための意識と姿勢
- スムーズな握り替えを行うための捕球とステップの工夫
- 送球方向に応じた柔軟な捕球位置の取り方
- シングルハンド捕球を成功させるための止まる技術
これらのポイントが気になる方は、ぜひ動画で実際の動きを確認してみてください。他の動画では別の選手による守備のアプローチも紹介されています。自分に合ったやり方を見つける参考になるはずです。


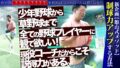
コメント