プロ野球で生き残るために、何が必要か。ピッチャーとして第一線で戦ってきた森福允彦が、「コントロール力」「投球フォーム」「メンタルと感覚」「環境適応力」などについて、自身の経験をもとにリアルな言葉で語ります。本編では、社会人野球時代の教え、練習法、変化球の工夫、マウンド環境への対処法、怪我と付き合う方法など、一流の投手たちが実践してきた「生き残りの技術」が余すことなく紹介されています。
- 1. プロで生き残るための「コントロール練習」00:03
- アウトロー10球中6球の課題
- 腰・膝・足で支えるコントロールの基礎
- 2. 投球フォームの探求と修正 02:58
- トルネード気味の独自フォーム
- ライン・沈み込み・蹴り出しの感覚調整
- 3. 感覚と視野・右手の使い方のこだわり 07:20
- リリース再現性と右目・左目の視野差
- サイド・アンダー特有の右腕操作
- 4. プレート位置とマウンド整備の工夫 14:18
- ステップ位置・踏み込み角度の調整
- 硬いマウンドの対処と削る工夫
- 5. 球場環境と気象条件の影響 21:34
- 屋外・屋内、風向き、観客目線への対応
- 球場ごとの変化球の変化と投球感覚
プロで生き残るための「コントロール練習」00:03
アウトロー10球中6球の課題
社会人時代に野村監督から言われた「外角低めに10球中6球投げられないとプロでは通用しない」という教えを胸に、ひたすらアウトローへの投球を練習してきた経験が語られます。
腰・膝・足で支えるコントロールの基礎
コントロールには手先より下半身、特に「腰の位置」「お尻の使い方」「踏み出し足の向き」が重要であるとされ、ステップ位置による投球方向の違いも解説されます。
投球フォームの探求と修正 02:58
トルネード気味の独自フォーム
体をひねることで勢いをつけるトルネード系のフォームにおける、開きを我慢するための工夫や、上半身の使い方が語られます。悪いときのフォームの特徴(開きが早いなど)も具体的です。
ライン・沈み込み・蹴り出しの感覚調整
「この位置にグラブを置けば投球が安定する」「この角度で沈み込めば再現性が高まる」といった繊細なライン意識が、再現性と安定感につながるポイントとして紹介されています。
感覚と視野・右手の使い方のこだわり 07:20
リリース再現性と右目・左目の視野差
効き目(利き目)によってリリースポイントの見え方が変わり、フォームにズレが生じるという視点から、構え位置や目線のコントロールも重要な要素とされています。
サイド・アンダー特有の右腕操作
「右手をどう振るか」「どのラインを通すか」など、特にサイドスローやアンダースローの投手にとって、腕の角度と位置取りが制球力に直結することが語られています。
プレート位置とマウンド整備の工夫 14:18
ステップ位置・踏み込み角度の調整
プレートを踏む位置と掘られた穴の活用で、微妙な投球角度・リリースのズレを補正する話や、足の削れた位置から逆算して立ち位置を調整する方法が紹介されます。
硬いマウンドの対処と削る工夫
マウンドが硬すぎて投げづらい場合の調整法として、「砂を埋めて視認性を下げる」「削って角度を変える」といったアナログながら実戦的な工夫が語られます。
球場環境と気象条件の影響 21:34
屋外・屋内、風向き、観客目線への対応
セ・リーグの客席の低さが視覚的プレッシャーになるという話や、甲子園の特有な応援と視線の交錯についての感覚が共有されます。
球場ごとの変化球の変化と投球感覚
「千葉マリンでは風で変化球の曲がりが大きくなる」「ドームでは打球が伸びやすい」「気圧の影響で球が浮く」など、球場ごとの特性をふまえた攻め方の工夫が紹介されます。
この動画から学べること
- 投手にとっての「コントロール」とは何かという本質的理解
- 体の使い方と足の踏み出しがもたらす投球への影響
- フォームの修正と再現性を高めるための感覚的練習法
- 球場・気象・マウンドの違いに適応するプロの工夫
- 右腕や視野といった身体感覚を重視した微調整の重要性
投手を目指す選手だけでなく、コーチや野球指導者にとっても非常に有用な学びが詰まった内容です。フォームや環境適応力に悩む選手にもヒントが多く含まれており、実践に活かせる知見が得られるでしょう。
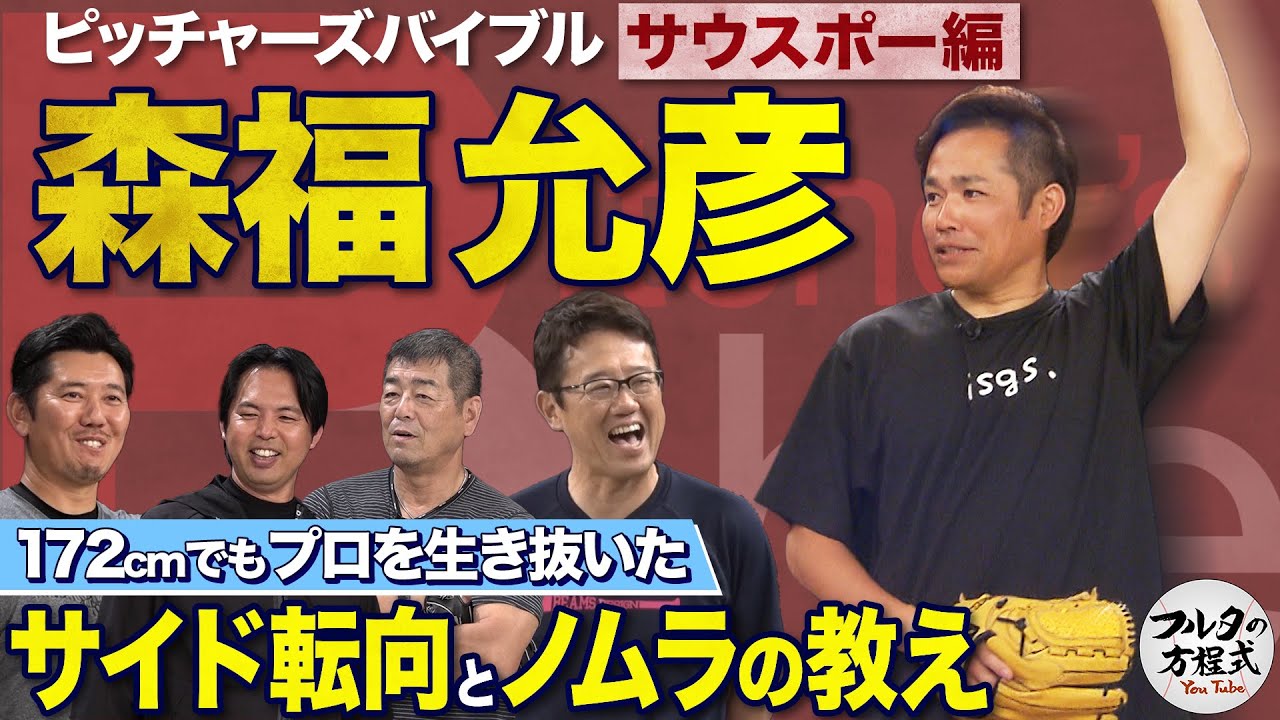


コメント