スローイング時のイップスについて、技術面からの改善方法と練習の工夫が具体的に語られています。学生に増えているスローイングのイップスに対し、技術的なアプローチと体の使い方を重視した対処法が紹介されています。
- 1. イップスの原因と技術的改善の入口 00:11
- 体の使い方の基本
- ドッジボールややり投げを活用
- 2. 軸足とリリースの意識づけ 01:38
- 抜けてもよいという前提でフォームを作る
- 遠投で体全体の動きを再確認
- 3. ポジション別の投げ方とその違い 02:59
- ピッチャーと野手のリリースの違い
- 条件反射で出るイップス
- 4. 実戦的なキャッチボールの意識 06:56
- 足を使った大きなフォームの重要性
- 遊び感覚を取り入れた練習
- 5. グラウンド状況による守備対応の違い 09:24
- 人工芝と天然芝・土での守り方の違い
- バウンド予測と構えの工夫
イップスの原因と技術的改善の入口 00:11
体の使い方の基本
スローイングで悩む選手の多くは、技術的な問題をきっかけにイップスに陥っています。まず左足にしっかり体重を乗せ、後方から腕を振ることができる形を作ることが重要とされています。
ドッジボールややり投げを活用
ドッジボールややり投げのような大きな動作が求められる動きを通じて、腕の振りを自然に学ばせる方法が紹介されています。特にやり投げは肘を曲げずに90度を保つ投げ方として効果的です。
軸足とリリースの意識づけ 01:38
抜けてもよいという前提でフォームを作る
初めの段階では制球を気にせず、ボールが抜けても構わないという意識で投げることが大切です。これにより、固まったフォームを解放し、自然な動きを身につけやすくなります。
遠投で体全体の動きを再確認
特にイップス傾向のある選手には遠投が効果的とされており、体全体を使ったスローイングを再認識する機会になります。
ポジション別の投げ方とその違い 02:59
ピッチャーと野手のリリースの違い
ピッチャーと野手では投げ方の根本が異なり、ピッチャーは体の後ろからリリースする意識が強い一方、野手は前で投げる感覚が自然です。この違いが投球時の違和感に繋がることもあります。
条件反射で出るイップス
特定のプレー条件下、例えばゲッツーや牽制といった場面でイップスが顕在化することがあり、ポジションやシチュエーションごとの投げ方の切り替えが困難な選手も多いと語られています。
実戦的なキャッチボールの意識 06:56
足を使った大きなフォームの重要性
ピッチャーのように大きく足を使い、体全体を動かす意識でキャッチボールを行うことで、送球時の安定感が向上するとされています。
遊び感覚を取り入れた練習
子供の頃から様々な角度やフォームで投げることで、柔軟なスローイング感覚が身につきやすくなります。あえて形式にこだわらず、遊び感覚を持つことが推奨されています。
グラウンド状況による守備対応の違い 09:24
人工芝と天然芝・土での守り方の違い
人工芝ではバウンド予測がしやすいため構えが安定しやすい一方、天然芝や土ではイレギュラーバウンドの可能性があるため、低い姿勢で警戒しながら守る必要があります。
バウンド予測と構えの工夫
土の硬さや質によっても守備の動き方が変わるため、グラウンド状況を考慮した対応力が求められます。天然芝ではバウンドが沈むこともあり、前に出やすい構えが有効とされています。
この動画から学べること
- スローイングイップスの技術的な改善方法
- 体の使い方を学ぶための練習法(ドッジボール・遠投など)
- ポジション別の投げ方の違いとリリース意識
- 遊びを取り入れたスローイングの習得法
- グラウンド条件による守備の対応と構えの工夫
これらが気になる人は、ぜひ実際の映像でニュアンスを確認してみてください。また、関連動画では別のプロ選手が同じテーマについて異なるアプローチを語っているので、自分に合った考え方を見つけてみましょう。
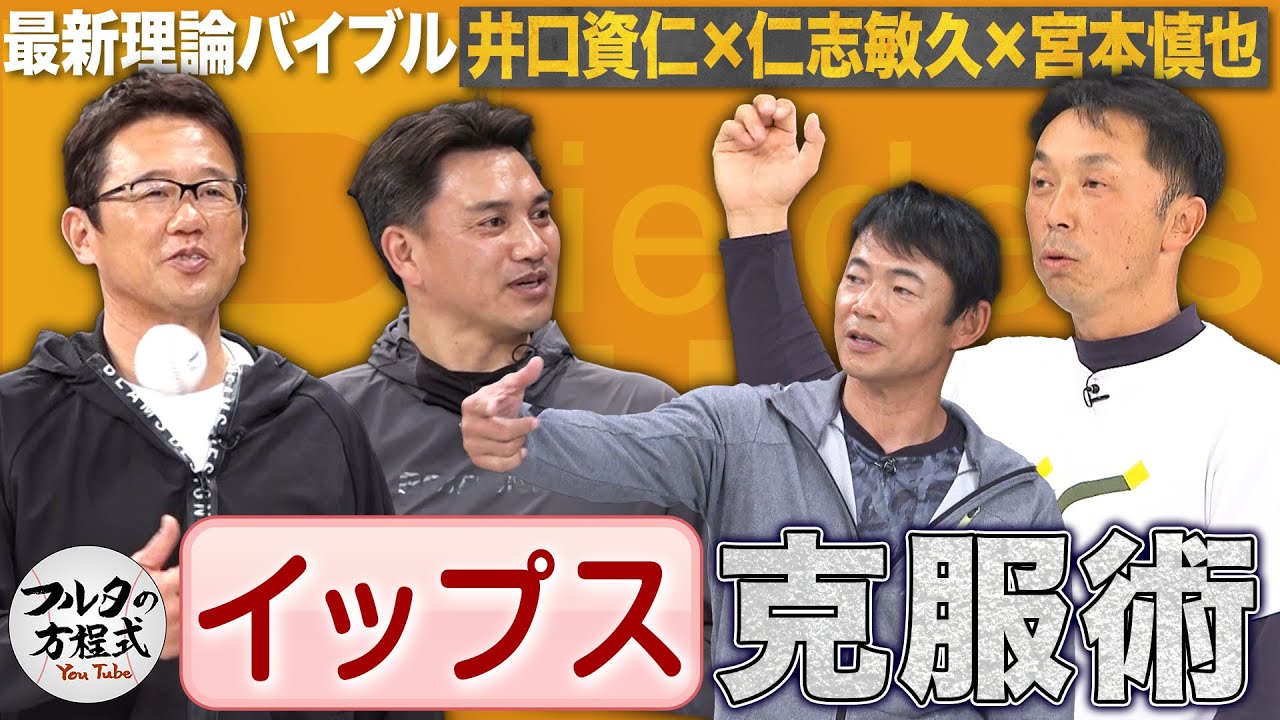


コメント