44歳まで現役を続けた和田毅が、引退直前の時期に取り組んでいたルーティンや体の使い方、シャドーピッチングの意識などについて、本人が映像を交えて詳しく語っています。毎日のストレッチ習慣やフォーム修正の工夫、下半身主導の体幹トレーニングがテーマとなり、若い選手にも参考となる内容が展開されています。
- 1. 股関節ストレッチとルーティンの継続【00:00】
- 毎日のクッション使用による股関節ケア
- フォームローラーとボールによる補助的なケア
- 2. シャドーピッチングで意識すべきこと【04:29】
- ボールなしで下半身主導の動きを確認
- 膝と股関節の連動確認によるケガ予防
- 3. 肩甲骨の動きと肋骨の安定性【07:14】
- 肋骨が動かない状態を保つ重要性
- 肩甲骨可動域の確保と肩への負担軽減
- 4. 体幹機能の低下と動作補正の悪循環【08:38】
- 体幹が効かなくなることで起こる代償動作
- 肘や肩への負担を避けるための体の使い方
股関節ストレッチとルーティンの継続【00:00】
毎日のクッション使用による股関節ケア
股関節の硬さを改善するため、三角クッションを使ったストレッチを毎日実施していました。数日で可動域に変化が出始め、継続が重要だと語られています。
フォームローラーとボールによる補助的なケア
背中や腰、首、臀部などをフォームローラーや硬めのボールで定期的にほぐし、疲労の蓄積や可動域の低下を防いでいました。
シャドーピッチングで意識すべきこと【04:29】
ボールなしで下半身主導の動きを確認
タオルを使わず、ボールも持たずにシャドーピッチングを行い、下半身が正しく使えているか、軸足の膝が早く割れていないかなどをチェックしていました。
膝と股関節の連動確認によるケガ予防
特に内転筋のケガを経験して以降、股関節の可動と膝の動きが連動しているかを常に意識しながら調整していたとのことです。
肩甲骨の動きと肋骨の安定性【07:14】
肋骨が動かない状態を保つ重要性
肋骨が上がってしまうと体幹の連動が切れ、肩甲骨の動きが制限されるため、肋骨を固定した状態でトレーニングを行っていました。
肩甲骨可動域の確保と肩への負担軽減
肋骨が安定することで肩甲骨の可動域が保たれ、結果的に肩への過負荷を防ぐことができると説明されています。
体幹機能の低下と動作補正の悪循環【08:38】
体幹が効かなくなることで起こる代償動作
体幹機能が低下すると、体を振るなどの代償動作が起こり、肩や肘への負担が増える原因になります。その連鎖を防ぐには、体幹を中心とした正しい連動を維持することが重要です。
肘や肩への負担を避けるための体の使い方
若いうちから目的を理解した上で正しいフォームでトレーニングを積み重ねることが、将来的なケガ予防につながると語られています。
この動画から学べること
- 股関節ストレッチとルーティンの重要性
- シャドーピッチングにおける下半身主導の意識
- 肋骨と肩甲骨の連動性の理解と応用
- 体幹機能の低下によるケガのリスクとその防ぎ方
これらの内容に興味がある方は、動画内の動きや説明を繰り返し確認し、自分の体の使い方やケア方法に活かしてみてください。特に、年齢や経験に応じた調整の方法は若い選手にとっても有用なヒントになります。
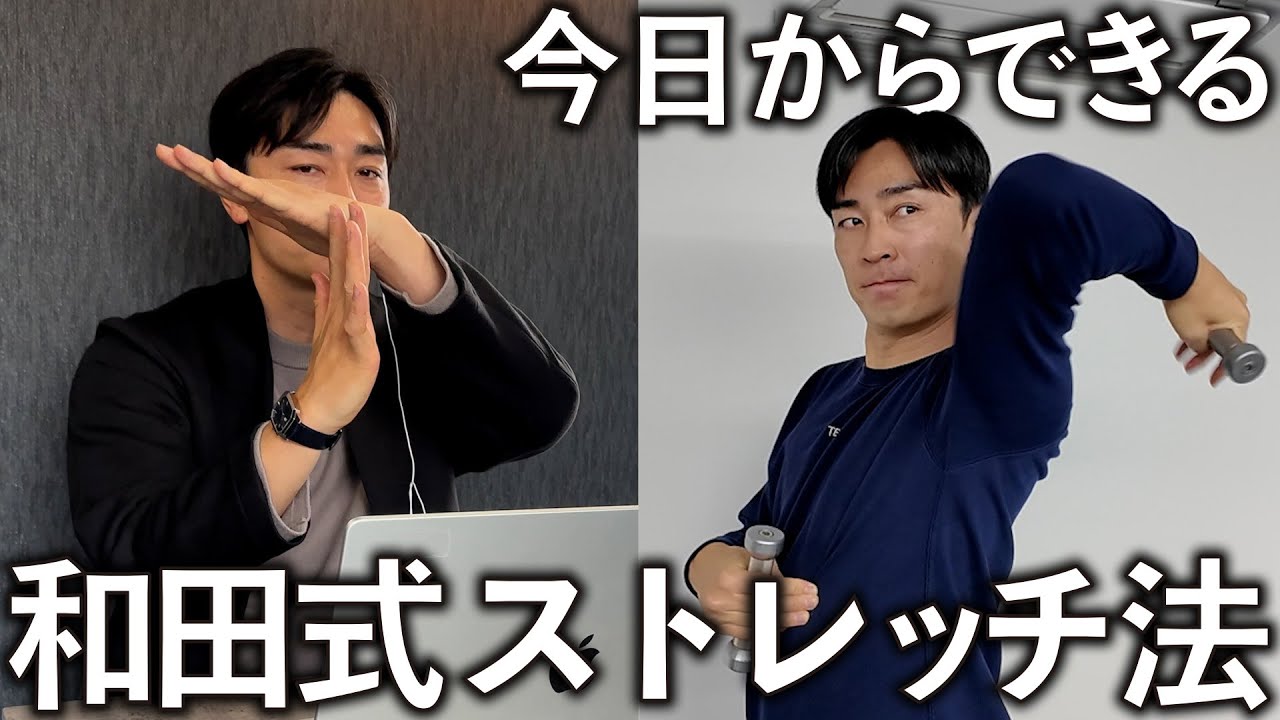


コメント