工藤公康を中心として、今中慎二・五十嵐亮太が近年の投球フォームの変化やテイクバックの意識について、具体的な動きとその意図が解説されています。肘や肩の負担を減らすためのフォームの工夫や、実戦での対応方法が紹介されています。
- 1. 投球フォームの変化と肘・肩への負担軽減【00:00】
- 肩を高く上げるフォームの利点
- 肘の使い方と内旋動作の変化
- テイクバックの大きさと安全性
- 2. リリース時の意識と調整の重要性【01:33】
- リリースポイントの安定性が最重要
- 投球動作中の遅れが与える影響
- アメリカと日本のボールの違いと対応
- 3. コントロール向上と視線の使い方【07:24】
- キャッチャーミットの見方
- バッターの動きと体の開きの関係
- 壁の意識と個人差
- 4. 下半身とグラブ側の連動【11:18】
- 軸を中心とした回転と連動
- 自然な連動のためのトレーニング
- 5. グラブの形状と使い方【14:03】
- グラブの硬さとボール処理の安定性
- 力の伝達とフィット感の重要性
投球フォームの変化と肘・肩への負担軽減【00:00】
肩を高く上げるフォームの利点
従来の内旋動作に比べ、肩を高く上げてから投げるフォームのほうが、肩や肘への負担が少ないとされています。実際に故障を減らした投手も出てきており、理論的にも高く上げることで負担が分散するためと考えられています。
肘の使い方と内旋動作の変化
最近では肘を強く内側に捻る動作が減少傾向にあり、より自然な流れで肘が上がるようなフォームが推奨されています。無理な力を入れず、肩や肘に負担がかからない動きが重視されています。
テイクバックの大きさと安全性
以前は大きく後ろに引くテイクバックが主流でしたが、現在では見た目以上にコンパクトにまとまった形が増えています。これは滑るボールへの対応や、リリースまでの加速を安定させるためで、怪我のリスクも低減できます。
リリース時の意識と調整の重要性【01:33】
リリースポイントの安定性が最重要
フォームの個人差がある中で、もっとも重要なのは「最終的にボールをリリースする位置が安定しているか」です。リリース位置さえ安定していれば、それまでの手の使い方にはある程度の自由があると述べられています。
投球動作中の遅れが与える影響
大きなフォームで遅れてしまうと、肘や肩に負担がかかります。遅れを生まないためには、加速ポイントを前方に設定して素早く振り抜くことが求められます。
アメリカと日本のボールの違いと対応
アメリカのボールは滑りやすく、日本のボールはしっとりしているという特徴があります。そのため、アメリカではボールを強く握る傾向があり、それがフォームや回転に影響を与えます。環境に応じた調整が必要とされています。
コントロール向上と視線の使い方【07:24】
キャッチャーミットの見方
キャッチャーミットをずっと見ていると体の開きが早くなる傾向があります。そのため、一度視線を外してから改めて見ることで、開きを抑える工夫が紹介されています。
バッターの動きと体の開きの関係
体が開いてしまう要因として、視線やタイミングの取り方が挙げられています。バッターの反応を読みつつも、フォームの崩れを防ぐには意識の分散が必要です。
壁の意識と個人差
下半身で壁を作る選手、グラブ側で作る選手など、意識する部位には個人差があります。どの方法が合うかは選手次第で、重要なのは「どこかで壁を作る」ことです。
下半身とグラブ側の連動【11:18】
軸を中心とした回転と連動
足が着いた時点で軸を固定し、そこを中心に体を回転させることで安定したフォームを実現します。この動きの中で下半身と上半身、グラブ側の腕が連動していくことが重要です。
自然な連動のためのトレーニング
連動を意識しすぎると特定の部位に意識が集中し、他の動きが死んでしまうことがあります。そのため、意識せずに自然と連動する動きを作ることを目的としたトレーニングが紹介されました。
グラブの形状と使い方【14:03】
グラブの硬さとボール処理の安定性
ライナーや強い打球を処理する際、柔らかいグラブだと弾かれる恐れがあります。硬めのグラブを使い、しっかりと閉じる工夫をすることで、安定してボールを処理できます。
力の伝達とフィット感の重要性
投球時に力がグラブ側に逃げないようにするため、しっかりとしたフィット感が求められます。手首が負けないように固定するため、マジックテープで調整する方法も紹介されています。
この動画から学べること:
- 肘・肩への負担を軽減するフォームの工夫
- 安定したリリースを実現するための調整方法
- ボールや環境に応じた投球フォームの変化
- コントロール向上のための視線と体の使い方
- 下半身との連動と軸意識の重要性
- グラブ選びとボール処理の工夫
これらのテーマに興味がある方は、ぜひ実際の映像で動きやニュアンスを確認してみてください。また、関連動画では他の選手の異なるアプローチも紹介されているため、自分に合ったスタイルを見つける参考になります。
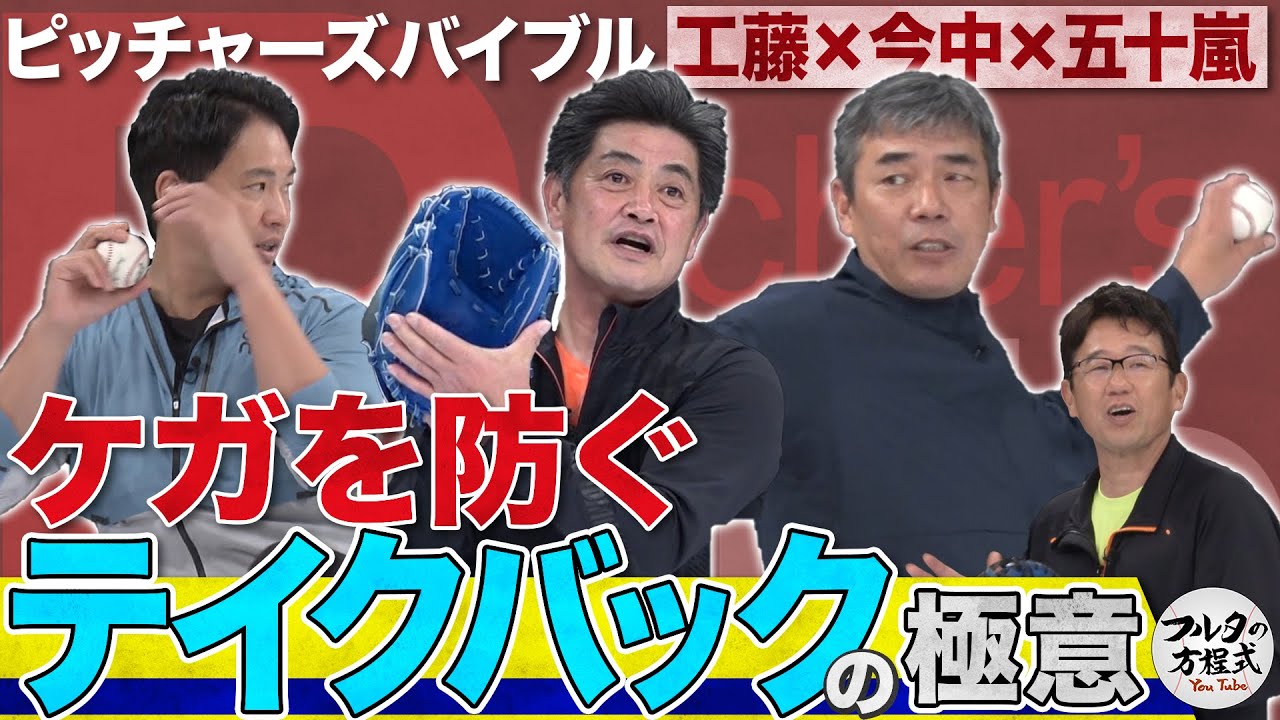


コメント