斉藤和巳と五十嵐亮太によってピッチングでの脱力と体幹主導の意識について、フォーム作りやトレーニングの視点から詳しく語られています。腹圧と呼吸を活用した投球技術の習得について、実践的な視点から深掘りされています。
- 1. 投球時の「開き」とリリースポイント【00:00】
- 速球を投げたいときに起こる開きのリスク
- 腕を振る意識とケガの関係
- リリースポイントの個人差と調整
- 2. プレートへの足のかけ方【03:54】
- 足のかけ方による安定感と力の伝達
- 軸足の意識と立ち方の工夫
- 3. トレーニングにおける意識の持ち方【07:37】
- 筋肉を意識しすぎないトレーニング
- 丹田と呼吸への意識
- 4. 腹圧と呼吸を活かした身体操作【12:18】
- 力を抜きながら力を入れる技術
- 日常から体幹を意識する工夫
- 5. 脱力と振られる感覚の重要性【20:02】
- 手足ではなく体幹で投げる意識
- ボールを投げる動作における脱力の効用
投球時の「開き」とリリースポイント【00:00】
速球を投げたいときに起こる開きのリスク
速い球を投げようとすると、上体の開きが早くなりがちです。意図せず開いてしまうと、抜け球やコントロールミスにつながることがあります。
腕を振る意識とケガの関係
「腕を振れ」という意識が強すぎると、上半身が先に開き、肩や肘への負担が増える可能性があります。腕は「振られるもの」と捉え、体幹主導のフォームを意識することが重要です。
リリースポイントの個人差と調整
リリースのタイミングには個人差があり、どちらが正解というものではありません。自分の投げ方に合ったリリースの強さやタイミングを探ることが必要です。
プレートへの足のかけ方【03:54】
足のかけ方による安定感と力の伝達
プレートへの足のかけ方には個人差がありますが、多くのプロは踵の一部をかけてバランスをとっています。力を入れやすく、体重移動もスムーズになる方法です。
軸足の意識と立ち方の工夫
プレートに足をかけない方がバランスをとりやすいと感じる選手もいます。軸足にしっかり乗る意識を持ち、まず安定して立つことが重要です。
トレーニングにおける意識の持ち方【07:37】
筋肉を意識しすぎないトレーニング
筋トレでは対象部位を意識するのが一般的ですが、野球においては過剰な意識が連動性を妨げることがあります。意識せずに使われる部位が自然に鍛えられるようなトレーニングが理想とされます。
丹田と呼吸への意識
下腹部(丹田)を中心とした体幹の意識が重要です。呼吸を活用し、トレーニングでもこのエリアを無意識に使えるようにする工夫が必要です。
腹圧と呼吸を活かした身体操作【12:18】
力を抜きながら力を入れる技術
最大限の力を発揮するには「力を抜くこと」が前提になります。抜くことで体の可動域が広がり、効率よく力を伝えられます。
日常から体幹を意識する工夫
トレーニングだけでなく、日常生活の中でも体幹を意識する習慣をつけることが重要です。立っているときや歩いているときにも体幹で支える感覚を身につけることがポイントです。
脱力と振られる感覚の重要性【20:02】
手足ではなく体幹で投げる意識
ピッチングにおいては、手足で投げるのではなく、体幹から腕が振られる感覚を大切にします。体の中心から動かすことで、より安定したフォームになります。
ボールを投げる動作における脱力の効用
脱力を意識すると、無駄な力が抜け、肩や肘への負担が軽減されます。速い球を投げたいときほど、意識的に力を抜くことが効果的です。
この動画から学べること:
- フォームの開きを防ぐための意識と工夫
- リリースポイントの調整方法と個人差の理解
- プレートへの足のかけ方と体重移動の関係
- 筋力トレーニングにおける体幹の使い方
- 脱力を通じた効率的な力の伝達とケガ予防
これらが気になる人は、ぜひ実際の映像でニュアンスを確認してみてください。また、関連動画では別のプロ選手が同じテーマについて異なるアプローチを語っているので、自分に合った考え方を見つけてみましょう。
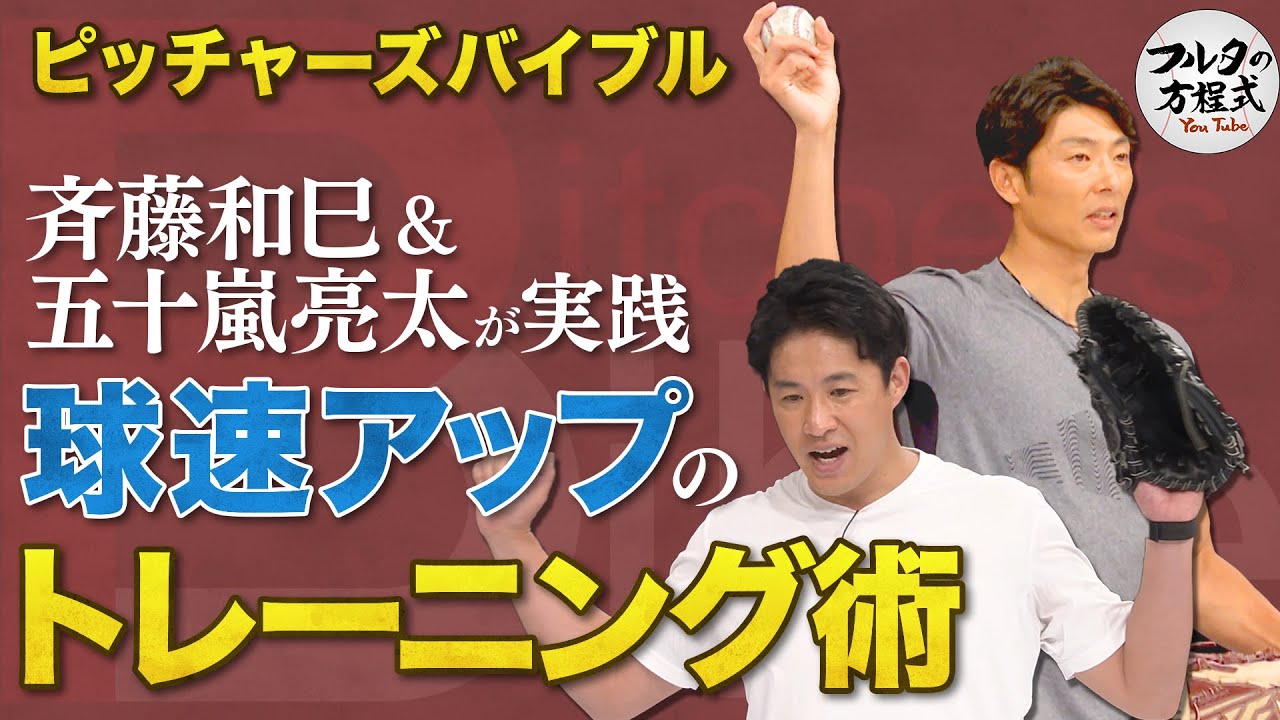


コメント